「袋帯 唐織 椿」
江州だるま糸使用 手織り
|
この文様ができたのは修学院離宮近くにある、一本の椿からです。7、8年前の晩春のことでした。落花した椿の綺麗なこと。しかも幹を中心に円を描いていました。その景色を写し、一部を文様にしたものです。椿は桜と共に帛撰が得意とする文様の一つです。
織の組織は唐織*1。経糸(たていと)・緯糸(よこいと)・絵緯(文様糸)にだるま糸*2を使っています。特に経糸は滋賀西浅井郡の西村さんのもの、江州だるま糸*3です。
本品は、日本の繭を、日本で手により糸にし、そして西陣にて手機で織り上げています。 |
*1唐織:一般的に唐織とは、能装束の中で女性役の着用するものをいいます(男性役は厚板)。必ずしも中国より伝わったということではありません。能装束のように装束というものは他に舞楽、神官、公家(現在は皇室)とあり、経糸は生、緯糸は練りのぬれ緯で織るのが普通です。そして昔はだるま糸でした。
*2だるま糸:だるま製糸機によって引かれた糸、座繰り糸の一つ。
*3江州だるま糸:現在では長浜市太田(西浅井郡)の西村さんと、大音の二軒のみが製糸。江州の特徴は、材料である繭に乾燥処理をしない生繭を使うところにあります。他の糸に比べ非常に強く、生産された糸のほとんどが琴、三味線の弦になります。通称は「琴糸」、故に文化庁文化財保存技術の指定を受けています。帛撰の唐織はこの糸を分けていただいて製織しています。現西陣織においては希です。
(2008年1月) |
  
|
【掲載誌】
江州だるま糸についての詳細と、この帯の色違い(オフホワイト)が淡交社刊行「京都で、きもの
Vol.5」(P96〜P101「高貴なる唐織の秘密を探して」)に掲載しています。
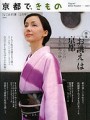  |

